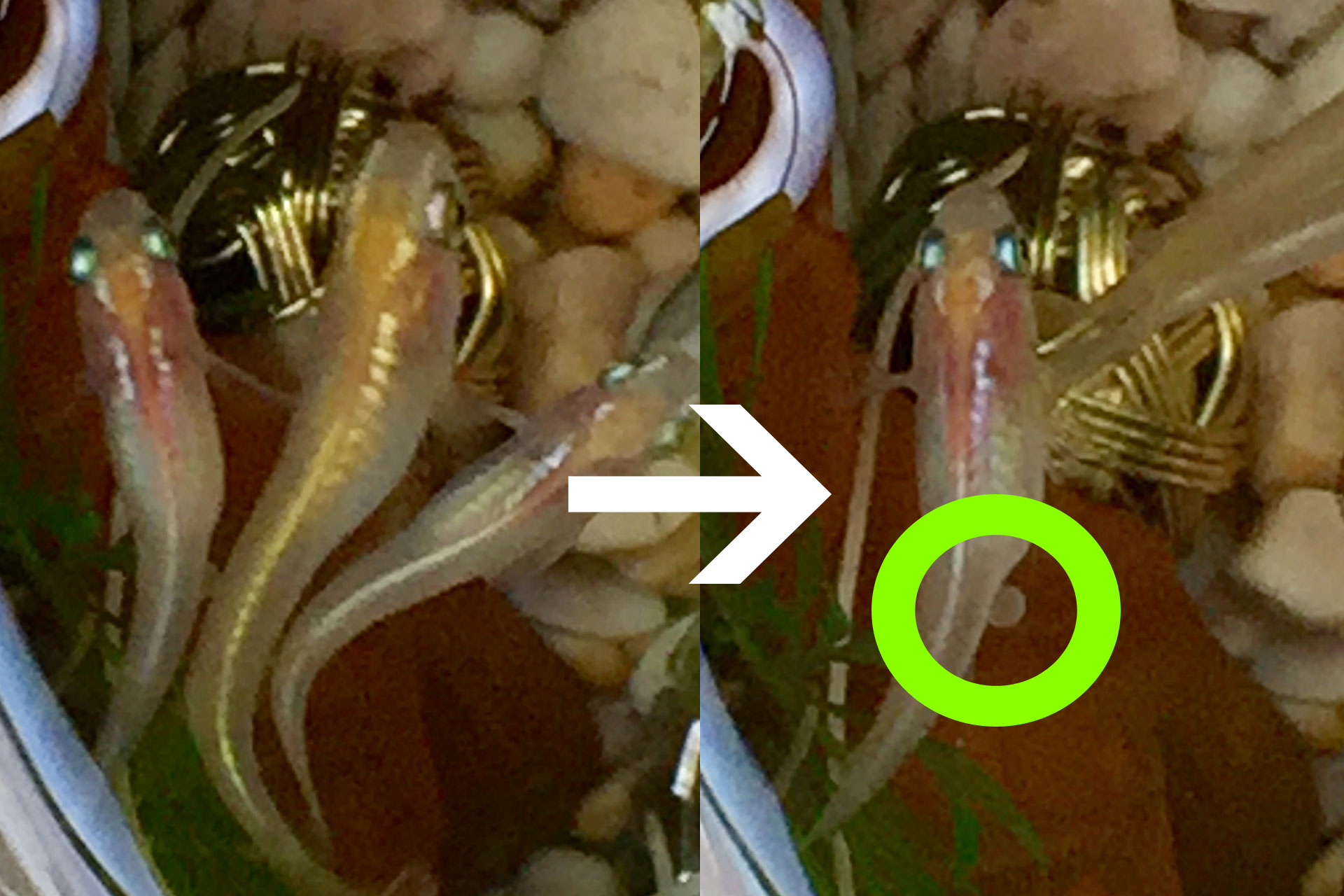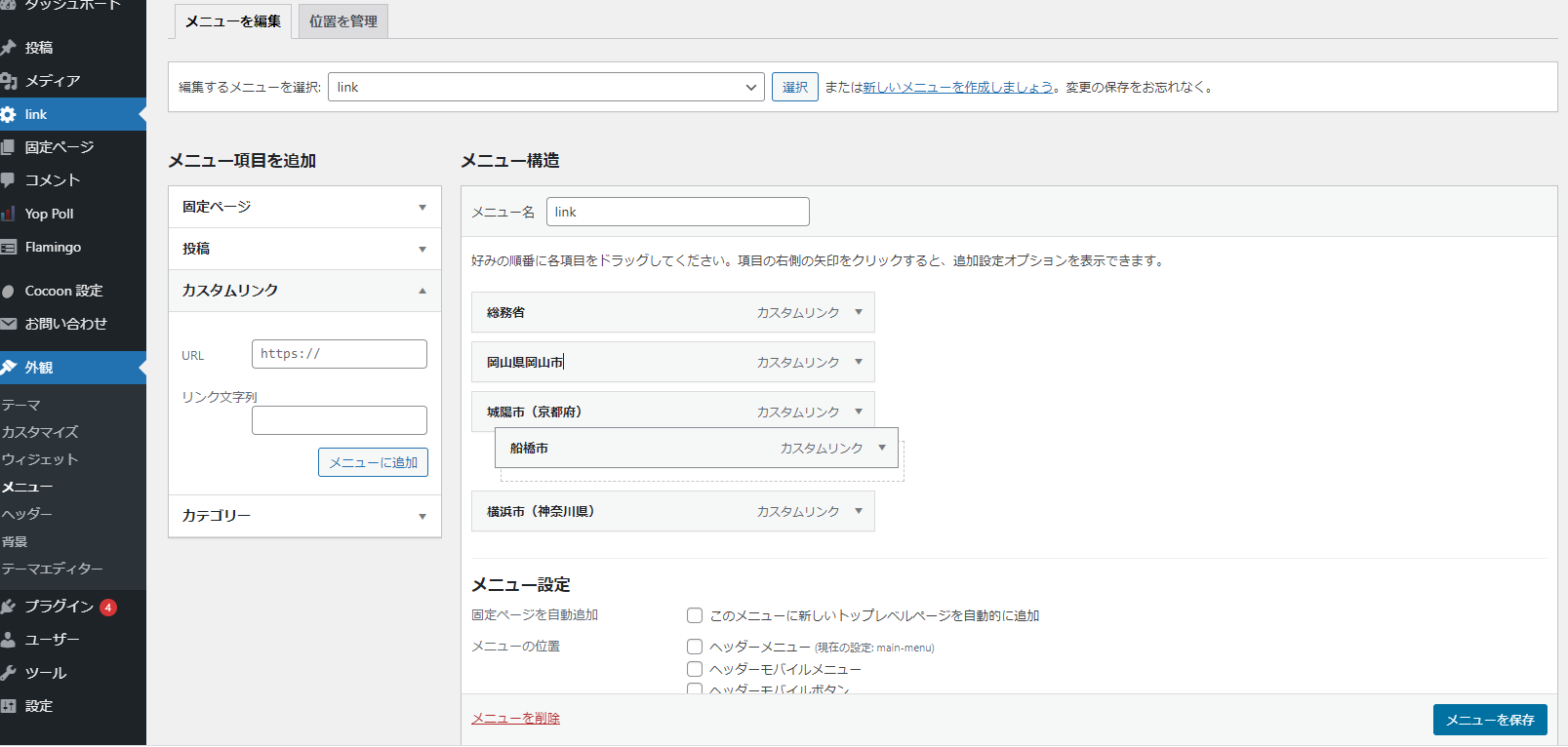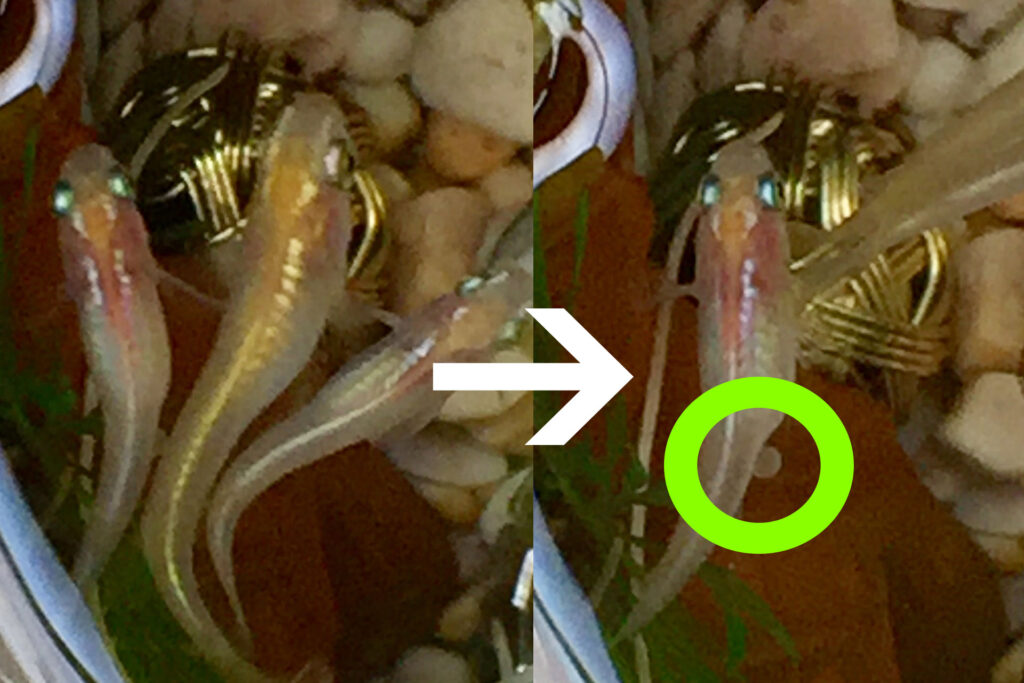
生後80日目で続々と産卵しはじめるメダカたち
前回、脱アンモニア水槽を作ってからメダカの生長が目視でわかるほど早くなっていました。
飼育中のメダカは14匹おり、うち2匹が2021年6月28日うまれです。
他の12匹は8月14日うまれ。
生後80日目と33日目の個体が入り混じっています。
最近ペアで行動するメダカが増えたように感じていたのですが、今回交尾の様子が映像に記録されていました。
通常のメダカは生後3か月から産卵開始
充分な栄養と照明、環境が整っていれば、メダカは3か月で生殖可能な成体へと成長するそうです。
たしかに飼育中のメダカも生後約3か月ですが、半月ほど早い計算に。
仮説でも良いので、早まった原因を論文から探してみました。
平均より早く産卵可能となった理由を論文から調べてみる
東京大学名誉教授 会田勝美氏と魚類生殖生物学者 小林牧人氏の研究内容。
お二人の書籍は農学部や水産学部の教材としても使われているそうです。
とはいってもメダカに関する記述はないので、どこまで当てはめて良いかは疑問が残ります。
テストステロンが今回のキーになりそうな内容でした。
こちらは九州大学農学研究員特任教授 松山倫也氏の研究内容です。
こちらでは生殖刺激ホルモンGTHについて学べました。
テストテロンとGTHを分泌させた理由があれば、個人的には納得できそうです。
テストテロンとは?

テストステロンは男性ホルモンとよばれるものですね。
肉・魚の内臓、魚卵などに多く含まれるコレステロールからテストステロンは作られます。
これは魚類でも同じであると記載されていました。
魚類は水酸化酵素を用いてテストステロンを生み出しているようです。
フェニルアラニン水酸化酵素というらしいのですが、人間にはフェニルアラニン水酸化酵素欠乏症という病気が存在します。
フェニルアラニン水酸化酵素とは?
恩賜財団母子愛育会様の発表内容なのですが、この中に欠乏症に対する治療用食品が記載されています。
デンプンです。
つまり豆でした。
たしかに飼育中の水槽には豆苗を植えています。
しかしデンプンは子葉に蓄えられており、マメ科は子葉のデンプンを用いて成長するものです。
ただ、豆苗が成長するに伴い浮島が沈みはじめ、たしかに小さな葉はメダカに食べられています。
落ちた葉も水中に溶けている状況です。
豆苗を植えっぱなしにしていたことで、水中のデンプン量が増えたのかもしれません。
生殖刺激ホルモン(GTH)とは?
ペプチドホルモンとそのキナーゼ型受容体による植物における細胞の伸長の制御
脳下垂体でつくられる糖タンパク質ホルモンをGTHとよぶそうです。
このGTHを放出させる生殖刺激ホルモン放出ホルモン(GnRH)というものがあり、こちらはアミノ酸10個からなるペプチドホルモンだそうです。
ペプチドにはタンパク質を活性化させ、生理作用を早める効果があると高校で習ったことがあります。
ペプチドが多く含まれているのは、牛乳、魚、大豆。
豆苗はエンドウ豆ですので、ペプチドは含まれていないようですね。
ペプチドはどこから?
エンドウ豆は最近プロテインとしても有名になってきましたが、デンプン・タンパク質・食物繊維を主成分としています。
エンドウ豆のタンパク質には18種類のアミノ酸があり、うち9種は必須アミノ酸です。
特徴的なのはアルギニンという成長ホルモンを分泌させる必須アミノ酸が含まれていることです。
アミノ酸が2~10個結合したものをオリゴペプチド、それ以上をポリペプチドとよぶのですが、はたして10個ならGnRHなのか?が私にはわかりません。
キスペプチンがGnRHを分泌する?
岡山大学大学院教授 大塚文男氏の発表論文。
この中にキスペプチンの効果が記載されています。
しかし、魚類ではキスペプチンが作用しないとのこと。
哺乳類では生殖制御の鍵を握るキスペプチンがサカナでは別の機能をもつ
東京大学生物科学専攻教授および博士課程3年の発表論文。
GnRH分泌を阻害する要素がなかったのでは?
GNRH拍動抑制における心理的ストレス、無秩序な食事、低体重、過度の運動の関係性
ストレス・無秩序な食事・低体重・過度の運動がGnRH分泌を阻害する要素だそうです。
ストレスといえばセロトニンでの抑制が有名ですが、このセロトニンの原料となるのはトリプトファンです。
カツオ・マグロ・大豆・牛乳・チーズ・ナッツ・バナナに含まれているアミノ酸で、結果としてイライラを抑えてくれます。
トリプトファンは大豆には及ばないものの、エンドウ豆にも含まれています。
メダカのストレス減少に果たして効果があるのか疑問は残りますが、あらためてマメ科のパワーを再発見いたしました。