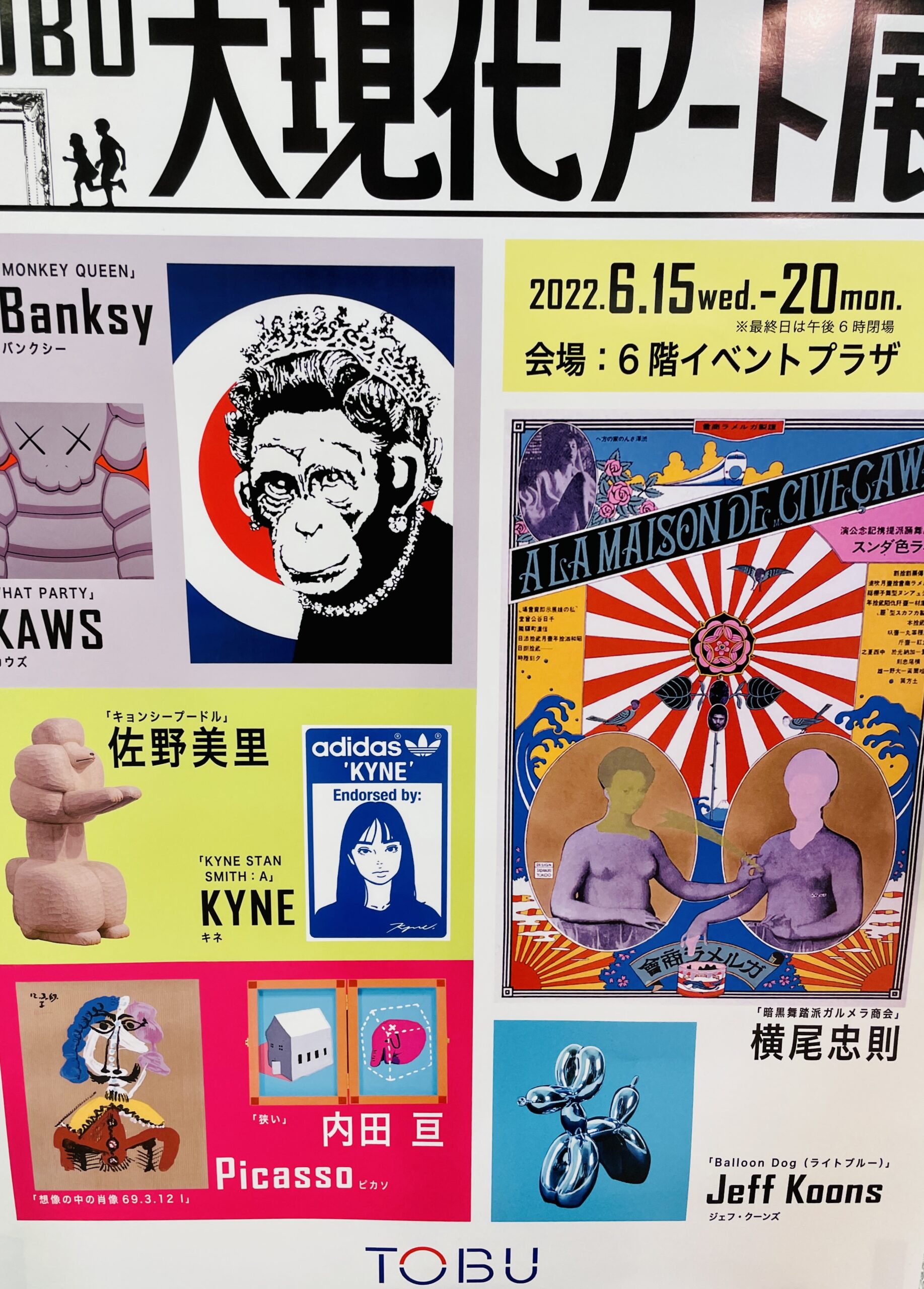2015年公開 ニール・ブロムカンプ監督作品
アカデミー賞ノミネート作品「第9地区」の監督
SONY PICTURES「チャッピー」
死にたくないロボット

SF作品ですが、この監督の作品はいつも道徳的要素を孕んでいます。
ロボットカッコイイーみたいなストーリーではありません。
上司の命令に背き、ディオン博士は人間の知能をロボットにインストール。
しかし、3名のギャングによってロボットは奪われてしまいます。
その後、知性を持ったロボット「チャッピー」は、自身の寿命を知り、生きることを目的とします。
立ち位置によって変わるテーマ

後半の盛り上がり、ラストの衝撃など、エンタメとしても見応えがある作品です。
公開時にはエンタメSF作品として楽しんでおりました。
しかし、教育に片足突っ込んだ状態で見ると、全編を通して考えさせられたのは「教育」について。
「学校の求める教育」と「子供が求める教育」のギャップが浮き彫りになっています。
教育とは?
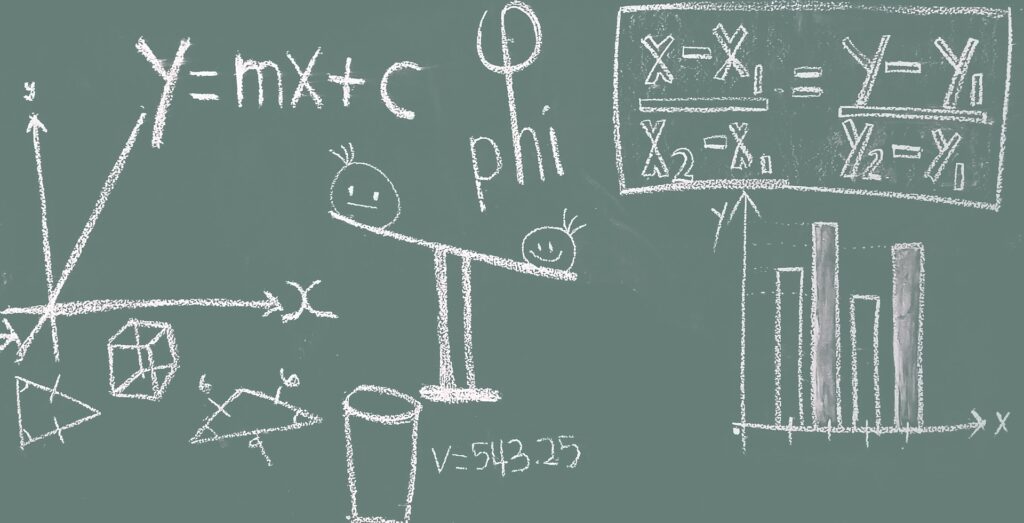
子供にモノコトを教えるとき、単語などの「正しさ」が先行します。
作中ではディオン博士がその役を担っています。
共通の単語がなければ、そもそも会話が成立しないので、正しさを教えることは正しいのですが…
ギャングによる教育

子供ほどの知能を持つチャッピーは、生みの親であるディオン博士ではなく、ギャングの知恵を積極的に学んでいきます。
「威圧させる歩き方」「脅し方」「銃の使い方」「手裏剣の投げ方」などなど。
学校で子供がそんなことを教わっていたら、親は卒倒するでしょう。
しかし社会で実用的なものは、知識や道具を使ってリソースを得る手法です。
生き残り方の教育

ギャングの教育内容は、作中社会での生き残り方。
生きることを目的としたチャッピーにとっては、最も効率的な教育であったと解釈できます。
作中でチャッピーが死ぬまでの猶予は、僅か5日。
「バナナ」の正しい発音を学んでも、生き残ることは達成できなかったのです。
教育の抱える課題

多様な職種が生まれる現代。
毎日のように新しい仕事が世に出ています。
教育は均一でありながら、職業は千差万別。
大人と子供の考える教育ギャップは日に日に大きくなっていると言えます。
チャッピーの決断

加速が続く社会において、企業が求める人材は経営理念に沿った判断と実行力のある人間。
チャッピーは最後に大きな判断を下します。
ギャングから「生き残る術」を学んだチャッピーの選択により、映画は衝撃的な最期を迎えます。
教育者が見たら「反道徳的」「行儀が悪い」と言いそうなラストです。
親の立場で見ると、最後はどう感じるのでしょうね…